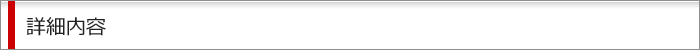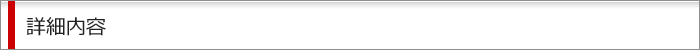| 囲碁とは?? その効能とは?? 部会からです。!! |
|
日本の囲碁の歴史は古く、枕の草子や源氏物語にも囲碁を打つ場面が多く書かれています。戦国時代では、碁を好む武将が多く、真田一族や武田信玄も相当な打ち手だったと 伝えられています。さらに江戸時代には、四つの家元制度が生まれ、しのぎを削って競争し 技量が飛躍的に発展し、庶民の間にも一層広まっていきました。
現在、多くのゲームがありますがが、囲碁ほど面白いゲームはありません。囲碁の基本は、地(じ、目の数)の多い方が勝つ、地取りゲームの面と、敵を攻め、石を取りにいく面があります。
その両方を考えて、構想を練って布石を打ち、中盤の戦いでは、攻める・切る・頭をたたく・絞りあげる・殺すなど攻撃的な言葉が目白押しです。終盤の寄せは、先手か後手かの差が大きく、やり方では逆転も生じ、最後まで気が抜けません。
しのぎをけずって戦った終局の白黒模様は、ひとつの芸術作品といえます。
三寿会の囲碁部会は、平成16年第31回大会以前の資料はありませんが、多分平成元年頃から始まっており、幹事は三橋忠雄様・古川正治様にお世話して頂いておりました。その後、平成20年の第36回より幹事は交代しております。
碁の諺に「着眼大局、着手小局]というものがあります、。物事を大きな視点から見て、小さなことから実践するという意味です。「着眼大局」とは、物事を全体的に大きくとらえ、広く物事を見て、その要点や本質を見抜くこと。「着手小局」とは、細かなところに目を配り、具体的な作業を実践をすること。まずは、全体を眺め、大きな方向性を定めて、そこから具体的な行動に落とし込み実践していく。
あるプロ棋士は 「碁を知らない人は、人生の半分の面白さしか知らない」 と言っています。
皆さんの残された人生を見直すのには、「着眼大局、着手小局」の精神が活かされている囲碁で感性を磨くのがベストではありませんか。ひとりでも多くひとが、碁に興味を持っていただき囲碁部会に参加して、人生の半分の面白さを見出すのにお遅いことはありません。
囲碁部会の定例会は、1月と7月の上旬に開催しており、普段の研鑚の成果を試すことになります。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。
幹事 川地光雄
|
|
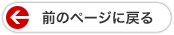 |